図書館で静かに本を読みたいのに、近くで長時間勉強している人がいてモヤモヤしたことはありませんか?
本来は誰もが自由に使えるはずの空間が、自習室のように占拠されているように感じる。そんな違和感の正体を、この記事では整理していきます。
一方で図書館で勉強せざるを得ない事情を抱える人がいるのも事実。
この記事では「図書館で勉強する人がうざい」と感じる理由を丁寧に紐解きながら、勉強する側・読書する側の双方に必要な視点を紹介します。
読んだあとには、図書館での過ごし方に少し優しくなれるかもしれません。公共空間を気持ちよく使うためのヒントをぜひ見つけてください。
図書館で勉強する人がうざいと感じるのはなぜ?
机を長時間占拠されると困る
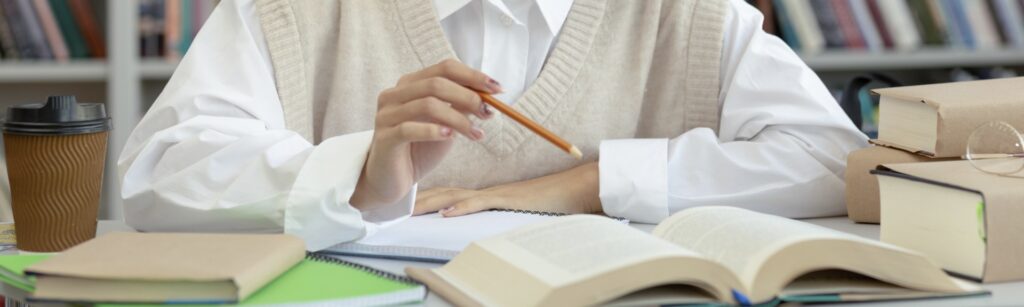
図書館で勉強している人が「うざい」と感じられる大きな理由の一つが、机を長時間占拠することです。
自分の参考書やノートを広げたまま何時間も席を離れない利用者がいると、ほかの来館者が座れず、本を読むことすらできなくなってしまいます。
図書館は誰もが自由に利用できる公共の場ですが、一部の人が独占してしまうとその公平性が損なわれてしまいます。
本を探しに来た人や、ちょっと座って読みたいだけの人にとっては、机の占拠は大きなストレスになります。図書館のスペースは限られているからこそ、お互いに譲り合う意識が必要です。
机は個人の所有物ではなく、みんなで使うものだという認識を忘れずにいたいものです。
小さな音でも集中を邪魔する
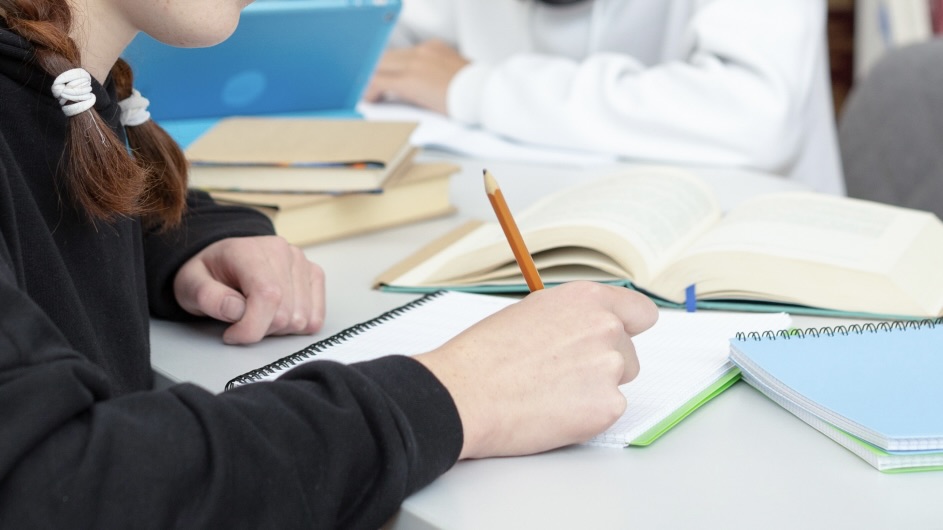
図書館は静寂が求められる場所です。しかし勉強している人たちが発する小さな音が、周囲にとっては大きなストレスになることがあります。
たとえばシャーペンをカチカチ鳴らす音、丸付けのシャッシャッという音、タブレットやスマホの操作音など、一つ一つは小さな音でも静かな環境では驚くほど気になります。
本人は意識していない場合が多いため、余計に厄介です。集中して本を読もうとしている人にとっては、たとえ些細な音でも気が散る原因になります。
図書館という空間では自分が出している音にもっと敏感になり、周囲への配慮を意識することが求められます。静かな環境を守るためには、ほんの少しの気遣いがとても大切です。
無言の空気で空間が独占される
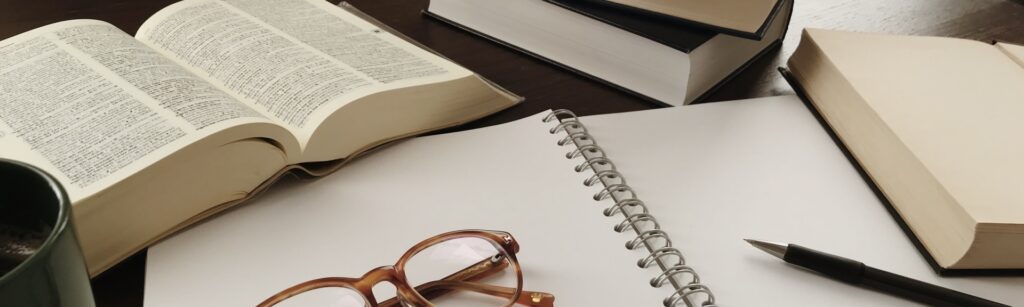
勉強道具を机いっぱいに広げることで無言のうちに空間を占領してしまう現象も、図書館で勉強する人への違和感の一因です。
机に参考書、ノート、飲み物などを置き、自習室のような空気を作り出すと周囲の人は自然と気後れしてしまいます。
本来は誰もが自由に使えるはずの空間なのに、勉強している人たちの「ここは私たちの場所」という無言の圧力によって利用の自由が暗黙に制限されてしまうのです。
悪意がないからこそ厄介で、周囲の人も注意しづらい状況が生まれます。図書館は一人ひとりが平等に利用する場であり、専有するものではないという意識を常に持ち続けることが大切です。
図書館で勉強するのは悪いことなのか?
勉強場所に悩む人たちの現実

図書館で勉強すること自体は必ずしも悪いこととは言えません。実際、自宅では家族の話し声や生活音で集中できなかったり、カフェや有料自習室を利用できない経済的事情があったりする人もいます。
とくに学生にとって、無料で静かに学習できる場所は限られており、図書館は貴重な学習スペースとなっています。
そういった背景を知らずに「図書館で勉強するのは迷惑」と一括りにしてしまうと、不公平に感じる人もいるかもしれません。
図書館という公共施設が多様な立場の人にとって「頼れる場所」であることを忘れてはならないと思います。
大切なのは「勉強していること自体」ではなく、使い方や周囲への配慮にあると言えるでしょう。
図書館の役割と「配慮」という前提
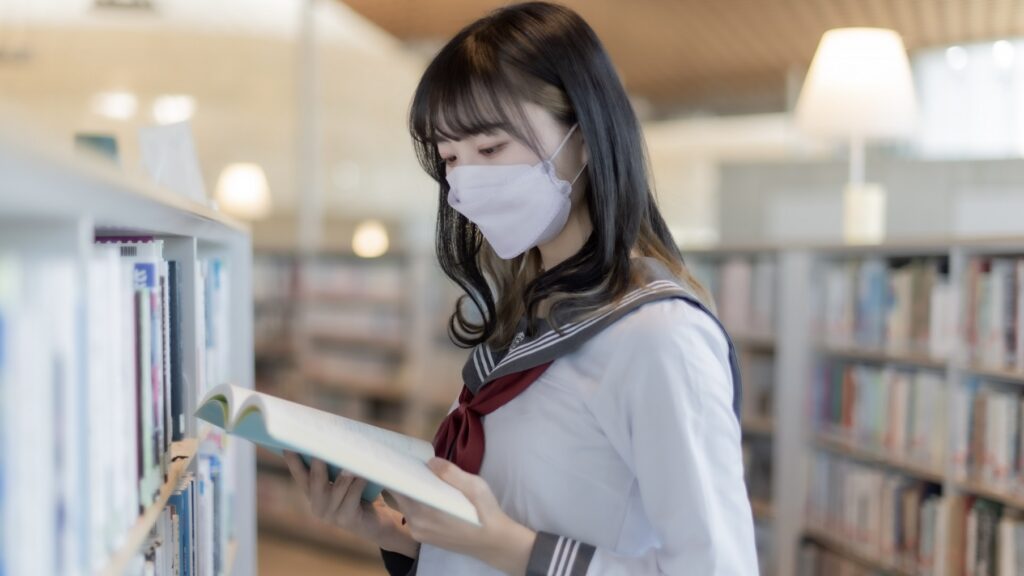
図書館は本来、資料の閲覧や調査・研究のために使われる場所として設計されています。そのため勉強という行為そのものが図書館の使い方としてズレているわけではありません。
しかし本来の目的に沿って利用するうえで必要になるのが「配慮」という視点です。どれだけ真面目に勉強していても、まわりに迷惑をかけてしまえば、それは正しい使い方とは言えません。
音や席の使い方、時間帯の選び方など、基本的なマナーを守ることではじめて勉強と図書館の役割が共存できる状態になります。
「勉強OKかどうか」ではなく、「勉強の仕方がどうか」に目を向けることがトラブルを減らす第一歩なのではないでしょうか。
勉強と読書、共存するためにできること
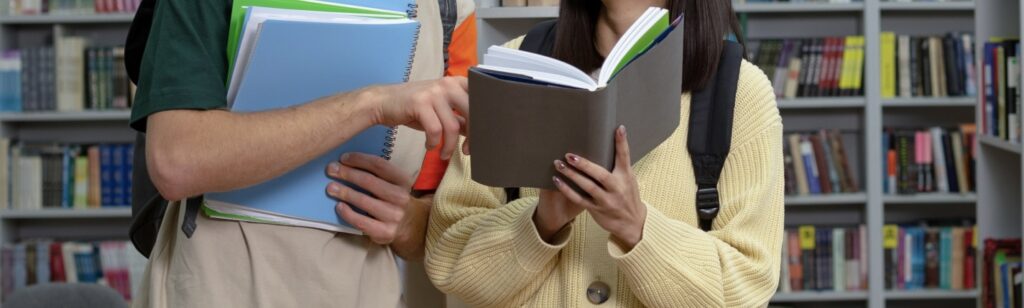
図書館を利用するすべての人が、勉強か読書かのどちらかに分かれるわけではありません。そのため、一方を排除しようとする考えでは根本的な解決にはなりません。
大切なのはお互いに快適に過ごせる工夫をすることです。たとえば机を広げすぎないようにする、タブレットの音量を切る、時間帯を選んで利用するなど、できる配慮はたくさんあります。
また図書館側が「勉強専用席」や「静音エリア」などのゾーニングを行っている場合は、それに従うことも有効です。
読書する側も「多少の物音は公共空間の一部」と理解していれば、相互理解は進みます。ちょっとした気遣いで、図書館はもっと気持ちよく使える場所になります。
誰も悪くないけれど、守りたい「公共空間」のバランス
勉強する側ができる配慮

図書館で勉強する際に心がけたいのは、「自分が今、公共空間にいる」という意識です。
机を何時間も独占するのではなく、利用者が多い時間帯には適度に席を譲る、音を出さないよう筆記具や端末の使い方に気を配るなど、周囲への配慮を忘れないことが大切です。
またもし近くで不快に感じる状況があった場合も自己判断で対処せず、スタッフに相談するのが賢明です。
周囲に迷惑をかけている自覚がなくても、図書館の空間を「みんなで共有している場所」だと理解していれば、自然とトラブルは減っていきます。
勉強に集中したいときほど、自分だけの世界に入りすぎないよう注意したいものです。
読書する側も持ちたい心構え

一方で読書目的で図書館を訪れている人も、公共空間であることを忘れずにいたいものです。
完全な静寂や理想的な環境を求めすぎると、些細な音や動きが気になってしまい、かえってイライラの元になってしまいます。
勉強している人にもさまざまな事情や背景があることを思い出せば、少しの寛容さを持てるかもしれません。
もちろん迷惑行為を黙認する必要はありませんが、いきなり否定から入るのではなく、まずは状況を見守る姿勢も大切です。
図書館を快適に使うには、お互いに「違う使い方をしている人がいる」ことを受け入れ、相手の存在を認めることから始まります。
図書館という空間を「みんなで心地よく」使うために
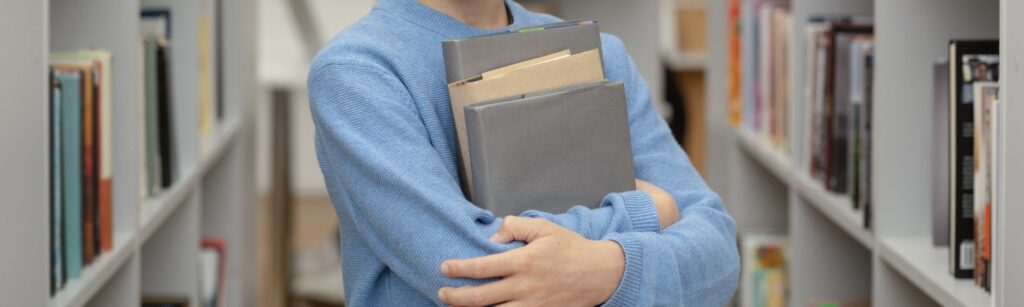
図書館は勉強する人、読書を楽しむ人、資料を調べに来た人など、さまざまな目的を持った人が集まる場所です。その中で全員が心地よく過ごすためには「互いに譲り合う」姿勢が欠かせません。
完全にストレスフリーな空間をつくることは難しくても、ちょっとした配慮や声かけ、時間帯の選び方などでトラブルを未然に防ぐことができます。
誰もが「自分の場所」と思い込みすぎず、「共有の場所で過ごしている」という意識を持つことが、結果的に一番快適な空間を作る方法なのかもしれません。
使い方の違いを否定するより共存の工夫をすること。それが図書館をもっと良い場所にしていく一歩になります。
まとめ
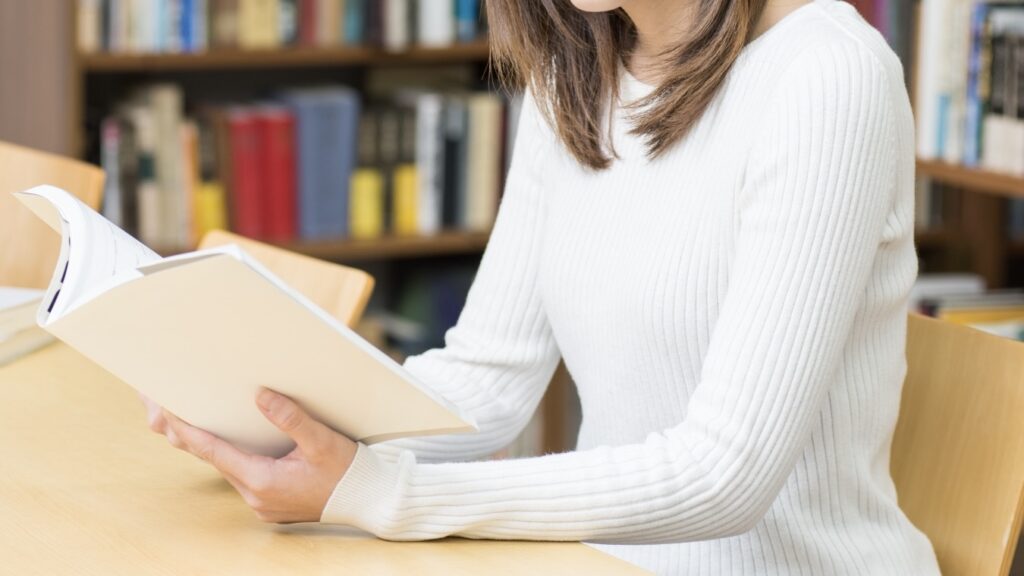
図書館は勉強する人、読書を楽しむ人、資料を調べに来た人など、さまざまな目的を持った人が集まる場所です。その中で全員が心地よく過ごすためには、「互いに譲り合う」姿勢が欠かせません。
完全にストレスフリーな空間をつくることは難しくても、ちょっとした配慮や声かけ、時間帯の選び方などでトラブルを未然に防ぐことができます。
誰もが「自分の場所」と思い込みすぎず、「共有の場所で過ごしている」という意識を持つことが、結果的に一番快適な空間を作る方法なのかもしれません。
使い方の違いを否定するより、共存の工夫をすること。それが図書館をもっと良い場所にしていく一歩になります。
編集後記

この記事を書きながら、今日ファミレスであった出来事をふと思い出しました。
今日はお出かけで少し遅くなってしまったので、近所のファミレスで夕食を済ませてしまおうということになったのですが、その判断がまさかの大失敗。
連休中ということもあり、周囲のテーブルでは少しお酒の入った方々が盛大に盛り上がっていて、家族連れだった私は正直「もう少し静かだったらいいのに…」と思ってしまいました。
でも彼らはルールを破っていたわけではありません。ファミレスにはお酒のメニューもあるし、楽しみ方も人それぞれ。自分が不快に感じたからといって、相手が悪いとは限らない。
そんな当たり前のことを改めて思い知らされました。(結局、最低限のメニューだけ注文して5分で食べて早々に退散しましたが…)
図書館でもファミレスでも公共の場にはさまざまな人がいて、それぞれが思い思いに過ごしています。その中で「自分がどうありたいか」を考えること、「周りへの小さな気遣い」を忘れないこと。
それだけは大切にしていたいと思いました。
誰も悪くない世界で、ほんの少し互いを思いやるだけできっともっと心地よい場所が生まれる。そんな希望を、私は信じています。

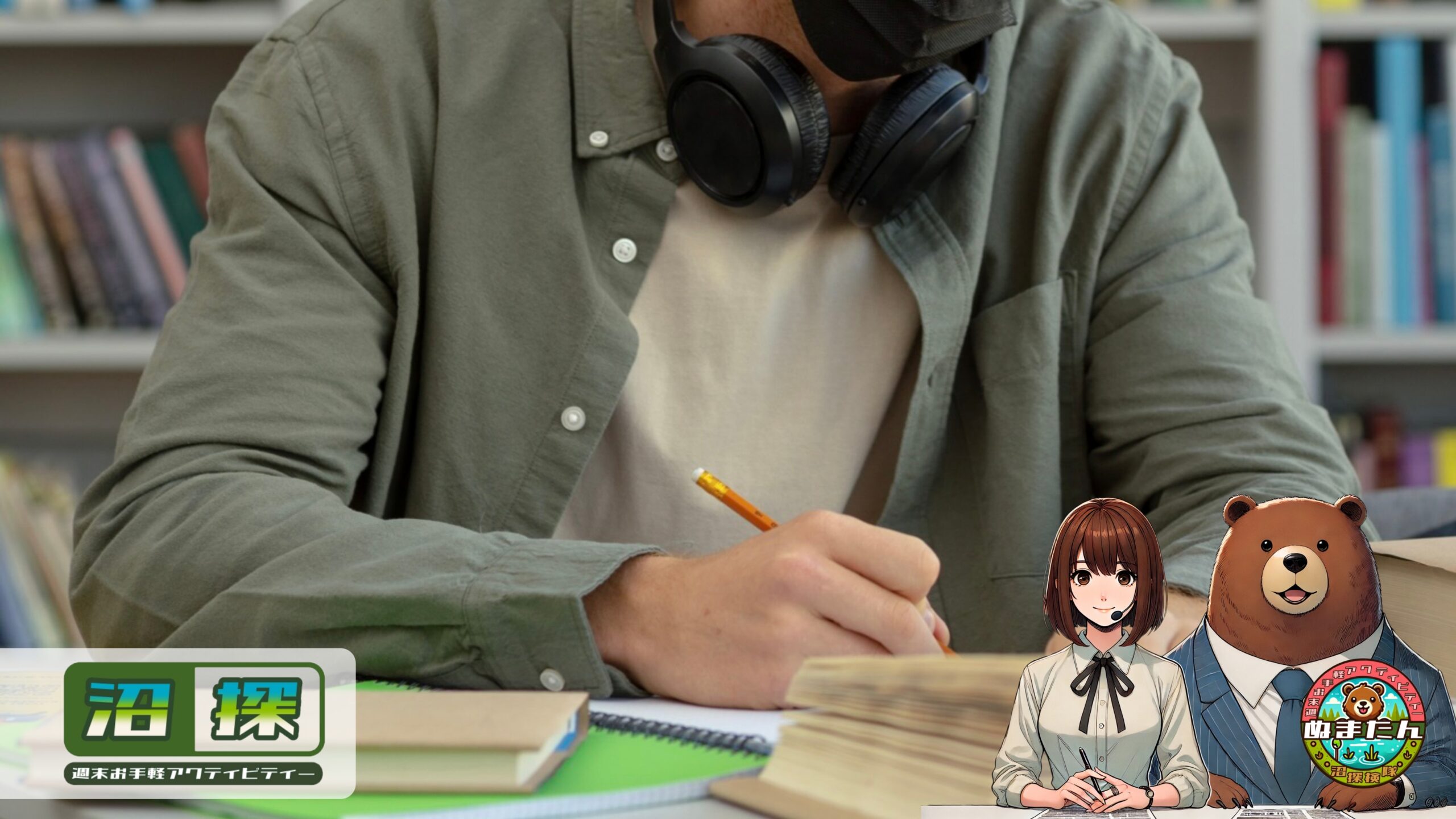


コメント