東京で生まれ育った人を見ると、なんとなく「ずるい」と感じてしまう ─ そんなふうに思ったことのある人に向けた記事です。
筆者は横浜で生まれ育ち、現在は東京在住。妻は東京生まれで、娘もまた東京で育っています。そんな私だからこそ見えてくる「東京のずるさ」や、「地方都市としての東京」の姿。
「東京生まれは本当に有利なのか?」という問いに対して、この記事ではその背景にある構造を静かに整理していきます。
視点を少し変えることで、自分の選択への見え方も変わってくるかもしれません。
東京生まれが「ずるい」と映る3つの観点
暮らしの便利さに支えられた日常
東京で生まれ育つと、生活の中に不便を感じる場面が少なくなります。鉄道やバスなどの公共交通機関が細かく張り巡らされていて、車がなくても日常の移動に困ることはほとんどありません。
さらに商業施設や病院、行政サービスも身近に揃っているため、生活を支える環境が自然と整っています。
加えて映画館や大型書店、展覧会やライブといった娯楽も近くにあるため、特別な準備をせずに楽しめるという点も特徴的。
こうした生活環境はあまりにも当たり前のものとして受け止められがちですが、地域によっては同じ便利さを得るために「時間や費用の負担」が生じる場面もあります。
身の回りに多くの選択肢が揃っているという点で、東京で暮らす日常は恵まれているように映ることがあるのかもしれません。
学びと成長の機会が身近にある

東京には、教育に関する選択肢が非常に多く用意されています。私立・公立を問わず学校の数が多く、進学先や校風の違いに応じて選べる範囲が広がります。
また学習塾や習い事の教室も多様で、子どもの興味や得意分野に応じて通える場所が見つかりやすいという特徴があります。
さらに大学や企業が集中していることで、進学や就職活動にかかる移動や費用の負担も比較的少なく済む傾向も。
地方でも充実した教育環境を整えている地域は多くありますが、都市部に比べると移動の自由度や選択肢の幅に差が出ることもあるかもしれません。
学びの機会が身近にあることで、自分の将来を考えるきっかけや行動の選択肢が増えていく点が、東京育ちの大きな特徴のひとつといえそうです。
人とのつながりが築きやすい環境
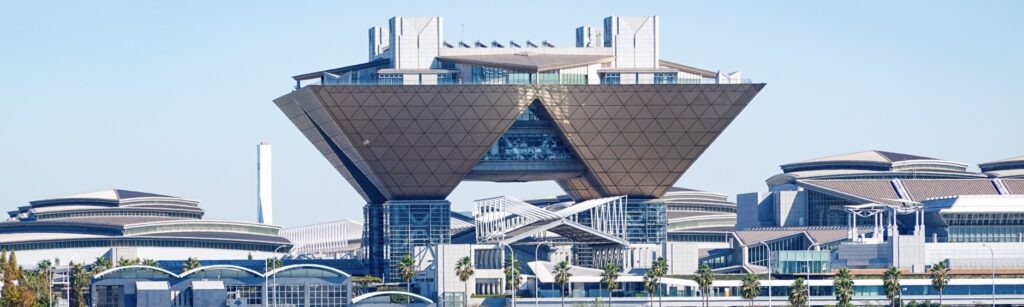
東京には人が集まってくるため、出会いのきっかけや人間関係の選択肢が自然と多くなります。
学校や職場だけでなく趣味のサークルやイベント、地域の取り組みなど、日常の中にさまざまな接点が組み込まれており、自分が会いたいタイプの人とつながる機会が得やすくなっています。
たとえば同じ趣味を持つ人を探したり、新しい交友関係を築こうとしたときに、その行動が実際につながりに変わりやすいのが東京の特徴です。
一方で地方では人口規模や地域の構造上、人間関係が固定されやすく、新しい関係を築こうとしたときに「既存のつながり」が壁になることもあります。
東京のように人が多く集まって関係を自由に選びやすい環境には、人とつながる際の柔軟さが備わっているといえるかもしれません。
東京生まれの生活に潜む意外なギャップ
繁華街には行かない東京生まれの日常
東京で生まれ育った人が、渋谷や新宿などの繁華街で日常的に過ごしているとは限りません。むしろ混雑や騒がしさを理由に、あえて足を運ばないという声もよく聞かれます。
東京で暮らす人たちの多くは、商店街や住宅地が広がる地域で生活しており、日々の買い物や食事も近所で済ませることがほとんどです。
都心の華やかなイメージは外から想像するほど身近ではなく、特別な予定がある時にだけ訪れる場所だという人も少なくありません。
もし「東京の人はいつも港区で遊んでいる」と感じているなら、それは実際の東京の暮らしとは少し違います。東京の日常は意外と静かで落ち着いていて、ゆっくり過ごす時間を大切にしている人もいる。
それは、地方での暮らしとも意外と近いのかもしれません。
「下町」を知れば見え方が変わる東京の姿

「東京生まれはずるい」と感じるとき、思い浮かべているのは、港区や渋谷区のような華やかなエリアではないでしょうか。
でも東京に根を張ってきた人々の多くは、昔から「下町」で暮らしてきた人たちです。江戸の町が作られた頃、武士たちは高台(山手)に屋敷を構え、町人たちは川沿いの低い地域で暮らすことになります。
その地域が、のちに「下町」と呼ばれるようになりました。つまり本来の意味で「東京生まれ」と言えるのは、「下町っ子」のことかもしれません。
では、彼らのことを「ずるい」と感じたことがあるでしょうか。むしろ、「せっかちで宵越しの銭は持たなくて祭り好き」だけな印象をお持ちの方も多いはず。
一度視点を変えてみると、見えてくる東京の姿も少し違ってくるかもしれません。
田舎がないことによる東京生まれの欠落感

東京で生まれ育った人には「田舎に帰る」という文化が存在しません。お盆や年末年始に親族が集まる場所がない、という感覚は意外と大きなもの。
地方出身の人が語る「夏になると祖父母の家で過ごした思い出」や「田園風景を眺めながら帰省する時間」には、どこか羨ましさを感じることもあります。
テレビや映画で描かれる日本の原風景に対して憧れを持っても、それが「自分のふるさと」として存在しない寂しさは、東京育ちの人ならではの感覚かもしれません。
また子どもを育てる立場になったときに「田舎に連れて行ってあげたいのに、行く場所がない」というもどかしさも出てきます。
こうした感情はなかなか他人には伝わりにくいものですが、「田舎がある」こと自体がひとつの価値であると気づかされる場面は少なくありません。
東京と地方にある裏返しの現実
東京の食は映えるけど財布に厳しい
東京では話題のカフェや人気のスイーツ店など、見た目も華やかで話題性のあるお店が至るところにあります。
写真映えする内装や盛り付けやSNSでの共有といった付加価値が重視され、味以外の要素が価格に上乗せされているケースも多く見られます。
もちろん特別な体験や非日常感を楽しむという意味では魅力的ですが、その一方で「美味しそうだけど高すぎて手が出ない」「混雑しすぎて落ち着かない」と感じてしまうこともあるでしょう。
外から見れば羨ましく映る東京グルメも、実際に暮らしてみると気軽に楽しめるようなものではないことに気づきます。
華やかに見せるための工夫が詰まった東京の食は「外向きの魅力」にはあふれていますが、日常的に満たされるものかというと、少し距離があるのかもしれません。
江戸に根付いた「外向きの飯」の文化

日本で外食文化が定着したのは、江戸時代の「江戸の町」が始まりだといわれています。当時の江戸は参勤交代によって、全国から大名や藩士が単身赴任で集まる都市。
家族と離れて暮らす彼らにとって自炊は現実的ではなく、飯屋や飲み屋は日々の暮らしに欠かせない存在になります。こうして外食は特別なものではなく、生活の一部として根づいていきました。
また藩士たちが江戸で飲み食いすれば、それが幕府経済にも還元される ─ そんな仕組みも背景にあったとされています。つまり江戸の食文化は、外から来た人を相手に発展してきた「外向きの飯」。
この構造は、現代の東京グルメにも通じています。人に見せることを前提としたスタイルは、江戸時代から続く「外の誰か」を意識した文化の延長といえるかもしれません。
地方の食は普通に旨くて満たされる

東京の食事がどこか物足りなく感じられる一方で、地方の食には「特別な演出がなくても普通に美味しい」という確かな魅力があります。
地方出身の知人からは「東京の米や魚は不味すぎる」といった声もよく耳にします。それは、新鮮な食材が身近にある環境で育った人ならではの、率直な違和感かもしれません。
テレビで見る「地元漁港の新鮮魚介類」や「産地の採れたて野菜」に心惹かれるのは、それが東京に暮らす人にとって非日常だから。一方、地方ではそうした食材が日常的に家庭の食卓に並びます。
知人のひとりは、帰省のたびに母親のごはんを食べすぎて太って戻ってくるほどで、「やっぱり実家の飯がいちばん美味い」と話していました。
東京が「見せる食」なら、地方は「満たす食」とも言えるのかもしれません。
まとめ
東京で育った人を「ずるい」と感じる気持ちは、暮らしの中にある違いから生まれることがあります。通勤や通学のしやすさ、進学や就職の選択肢の広さ、人との出会いやつながりの多さ。
そうした環境に触れると、地方での暮らしとは違う部分が見えてきます。ただその一方で、東京にも特有の事情があります。
繁華街に足を運ばない日常や下町に根づく空気感、田舎に帰るという体験が持ちにくいことなど、東京だからこそ欠けているものもあります。
さらに食の面では「見せること」を意識した東京の食と、「満たされる日常」がある地方の食。それぞれに違った良さがあります。
生まれた場所による環境の違いを知ることで、自分の立場や選択への見方も少しずつ変わっていくかもしれません。





コメント