「三笠焼き」と「どら焼き」って何が違うの?― そんな素朴な疑問を持った方に向けた記事です。
見た目も味もそっくりなこの二つ、実は呼び方に地域差があるだけ…と思いきや、名前の背景にはちょっと面白い歴史が隠れています。
この記事では「三笠焼き」と「どら焼き」の違いや由来をひもときつつ、「戦艦三笠」との意外な共通点、そして「三笠焼き・どら焼き」の新たな可能性まで一気に紹介します。
読み終わるころには、甘~い和菓子の名前がとんでもない世界史とつながっていたことに気づくはず。軽く読めて、ちょっと賢くなれる、そんなネタが詰まっています。
どら焼きと三笠焼きは同じものなのか?
江戸時代のどら焼きは四角い姿だった

現代のどら焼きは、丸くてふっくらとした形が一般的。ただ「江戸時代のどら焼き」は、今のものとはかなり違っていたようです。(Wikipedia)
一枚の皮を鉄板で焼いて、それを折りたたむようにして中にあんこを包む。つまり形は四角く、横からあんこが見えているような感じで、現代の「あん巻き」に近かったとも言われています。
「どら焼き」という名前の由来にはいくつかの説がありますが、「銅鑼のように丸く焼いたことから」という話が有名です。
ただ当時の形が四角かったことを考えると、「どら焼き」という名前は、わりと後の時代に名付けられたことが想像できます。
つまり「どら焼き的な和菓子」が先に広まり、徐々に丸い形となって「どら焼き」と呼ばれるようになっていった。それが「現代どら焼き」のザックリとした歴史です。
現代どら焼きは上野うさぎやから生まれた

「現在どら焼き」の一般的なスタイル、丸く焼いた皮を二枚重ねてあんこを挟んだ形は、大正時代に東京・上野で創業した和菓子店「うさぎや」が発祥とされています(諸説あり)。
「うさぎや」では丸い「どら焼き的な和菓子」を「編笠焼(あみがさやき)」として販売していたようで、これはおそらくですが、「見た目が編笠に似ていた」ことから名付けられたのかと。
この丸い「編笠焼」が人気となって丸い形が広まり、そしてどこかのタイミングで「どら焼き」という名前で定着していったのでしょう。
「江戸時代のどら焼きが四角くて一枚皮」だったのに対し、大正以降は「丸くて両面焼きの二枚重ね」が主流になった。
つまり「現代どら焼き」の姿は、この流れの中で自然に生まれてきた、ということのようです。
関西では奈良の山にちなんで三笠焼きになった

「どら焼き」と「三笠焼き」は何が違うのか? については、GoogleのAIさんが「同じです」と回答している通りです。
関西では「どら焼き」を「三笠焼き」や「三笠なんちゃら」と呼ぶことが多く、中でも「文明堂の三笠山」はもらって嬉しい頂き物として、贈り物界の絶対王者(私の感想を強く含みます)。
ちなみに「三笠焼き」という名前の由来は「奈良県の三笠山(現在の若草山)」で、そのこんもりと丸い形が、「どら焼き」の見た目と重なることから名付けられたんだとか。
つまり関西では、「あの形」を形容する表現は「銅鑼」よりも「三笠(山)」の方がインパクトがあって適切だったということでしょう。でも逆に、「あの山」を見たことがない地域の人たちには伝わらない。
つまり「三笠焼き」は関西で「どら焼き」を最も適切に表現する言葉。要は「同じ」ってことです。
どら焼き(三笠焼き)と戦艦三笠の意外な関係
日本海海戦を戦った「誇りの艦」が三笠だった

さて、関西では「三笠」と聞いたら「どら焼き的な和菓子」を、歴史好きは「戦艦三笠」をイメージしますよね?(やや圧)。なので戦艦の「三笠」についてもお話ししておきます。
明治時代、日本の命運をかけた日露戦争で主力艦となったのが「戦艦三笠」。1905年、日本海海戦で日本艦隊のリーダー艦として出撃し、ロシアのバルチック艦隊を迎え撃ちました。
指揮を取った東郷平八郎が、「皇国の興廃この一戦に在り」とZ旗を掲げたのもこの三笠。その海戦で日本艦隊は大勝利を収め、戦艦三笠は日本海軍の象徴的な存在となりました。
現在は横須賀の三笠公園で記念艦として保存されていて、一般公開もされています。
つまり戦艦の方の「三笠」は日本人の心に「誇り」として残り続ける、近代史のアイコンのような存在でもあるわけです。
名前の由来は同じく「奈良の三笠山」だった
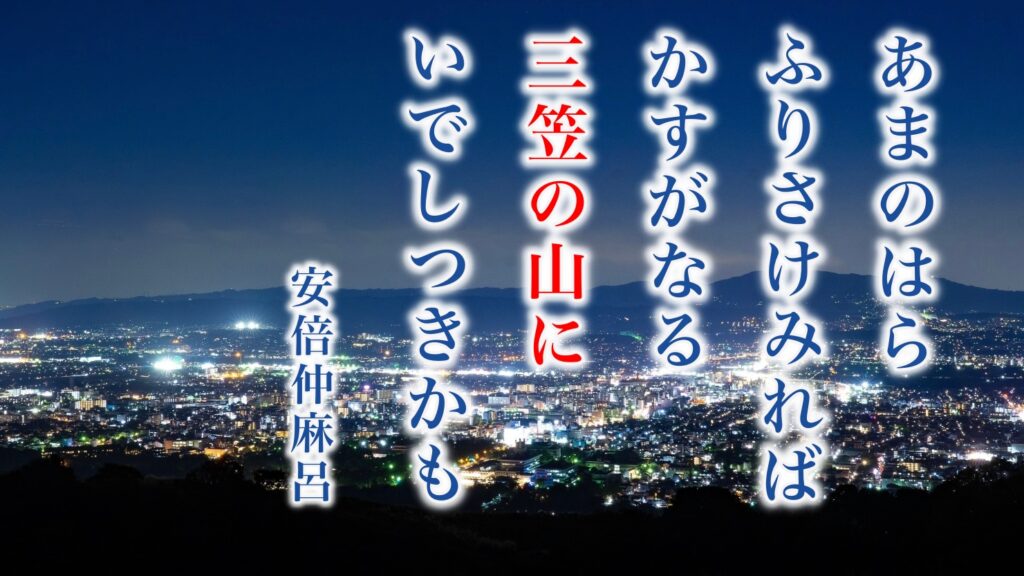
その戦艦「三笠」という名前ですが、こちらも同じく奈良県の三笠山(現在の若草山)にちなんで付けられました。
これは当時の日本海軍では、戦艦に「山の名前」を用いるのが命名ルールとしていたためで、別に「形が似ていたから」ではありません。
三笠山は古くから和歌や詩にも登場してきた山で、日本の美意識を映す存在として親しまれてきました。そんな美しさや響きが「艦名にふさわしい」と考えられたのかもしれません。
なお、戦艦三笠は日本国内で造ったものではなくイギリス製。発注したのは1898年(明治31年)で、4年後の1902年に日本へ引き渡されました。
この際、イギリス人が「The Mikasa is ready, sir.(お待たせしました、三笠です)」なんて言うわけないので、「三笠」という名前は日本海軍が決めたのでしょう。
関西人には「戦艦どら焼き」に聞こえていた説

さて、関西で「三笠」といえば「どら焼き的なものを連想されてしまう」ことを考えると、実は当時の人々が「戦艦三笠」と聞いて連想するイメージにも、「全国とは違い」があったのかもしれません。
連合艦隊の旗艦(日本艦隊のリーダー艦)としてロシアのバルチック艦隊との大海戦を指揮し、大勝利を収めた日本海軍の象徴的存在。
その戦艦三笠が、まさかの関西では「戦艦どら焼き」的な意味で解釈されていた可能性が浮上したわけです。これはもちろん冗談ですが…、表現の感覚が違えば、同じ出来事でも別の見え方がある。
まあでも、そんなズレを面白がれるのも、平和になった今だからこそかもしれません。
あと、ちょっと気になるのですが、関西の人は「ドラえもん」より「ミカえもん」の方がしっくりくるんでしょうかね…。
Z旗の真実はイギリス海軍へのリスペクトだった
「皇国の興廃この一戦に在り」という伝説の旗


この記事では戦艦三笠を「どら焼き戦艦」扱いしてしまいましたが…、最高にカッコよかった「戦艦三笠」の話もしておきます。
その日、戦艦三笠のマストに「Z旗」が掲げられた瞬間、日本艦隊の空気が変わりました。日露戦争の決戦、日本海海戦において戦艦三笠のマストに掲げられたのが「Z旗」。
それは「皇国の興廃この一戦に在り 各員一層奮励努力せよ」という、強烈なメッセージを意味していました。
でもこの「Z旗」、もともとは「タグボートを求む」や「投網中」といった全く別の用途で使われる国際信号旗で、「A旗〜Z旗」まで、そのデザインが決められています。
でも、日本艦隊の中では東郷平八郎がこの「Z旗」に別の意味を持たせたことで、「士気高揚の喝っ!」へと変貌したわけです。
戦艦三笠に掲げられた「Z旗」は、戦いの号令を超えた「最高にカッコいい三笠の象徴」として語り継がれています。
東郷平八郎は百年前のネルソン提督を真似した?

でも実は…、1905年の「東郷平八郎のZ旗掲揚」…、東郷オリジナルではない可能性があります。
なぜなら東郷が若い頃に海軍の研修で滞在していたイギリスには、すでに「士気を高める旗信号」の歴史が存在していたから。
その代表例は日本海海戦より100年も前。1805年のトラファルガー海戦で、イギリス艦隊のネルソン提督が掲げた「イングランドはすべての人間が義務を果たすことを期待している」というもの。
この「喝っ!」がイギリス海軍の伝統となったように、「東郷のZ旗」も日本海軍の伝説となりました。どちらも決戦前に「全軍の士気を上げる手段」として使われた点で同じ。
つまり「東郷のZ旗」は、100年前の英国式「渇っ!」を日本版にリミックスしたという見方もできるわけ。まさか「カレー」だけではなく、「Z旗」までが英国海軍由来だった?とは、ちょっと驚きです。
次の名物はこれだ!「よこすか海軍どら焼き(案)」

戦艦三笠と三笠焼き(どら焼き)は同じ由来で、「Z旗」はイギリスの戦術をなぞっていて、横須賀にはイギリス伝来の「海軍カレー」もある。ここまで来たら、もう一つ横須賀名物を増やすのはどうでしょう?
「よこすか海軍どら焼き」なんて、お土産にもうってつけ。例えば、どら焼きに「Z旗の焼印」を押したデザイン。海軍カレーとセットで出すもよし、三笠公園の売店で売るもよし。
ストーリーがしっかりしてるぶん、「手に取って語りたくなるお土産」になる。しかも名前は親しみやすく、味は誰でも知ってる安心感。学校や職場でも配りやすい個包装!
どうせなら佐世保バーガーのように認定制度を導入して、基準をクリアした市内の店舗のみが横須賀市から「Z旗焼印」の使用を許可されるようにしましょう。
これで横須賀市の産業振興とブランド化も図れます。
海軍カレーで街おこしをした横須賀市が、次に目指すべきは「和菓子による文化リミックス」。それを象徴する一品として、「よこすか海軍どら焼き(案)」は、これ以上ない新名物になるはずです。
あくまで「案(餡)」ですけどね、どら焼きだけに…。





コメント