「中央線と中央本線って、何が違うの?」─ そんな疑問を抱いた方に向けた記事です。
普段から中央線を利用している人でも、「オレンジの電車は中央線?あずさ2号が中央本線?」と混乱したことがあるのではないでしょうか。
この記事では、東京の電車が「呼び名も路線も複雑になった」経緯をわかりやすく解説。
読み進めることで、東京の電車がグチャグチャなった「トホホな事情」と、最近のJRが「ハッ!」と気付いて導入してしまった「超シンプルな解決策」についても触れていきます。
新宿~中野間でサクッと読めるボリュームで、話のネタにもなる内容です。ぜひ読んでみてください。
中央線と中央本線って何が違うの?
そもそも「本線」って何なの?

ではまず、「本線とはなんぞや?」について解説します。JR線における「本線」とは、かつて国鉄が整備した「特に重要な線路」を意味するもの。
これは「主要都市をつなぐ大動脈」にあたる線路が該当し、その本線から「独立線・支線」と呼ばれる線路が「木の幹と枝」のように伸びています。
実際に東京〜神戸を結ぶ東海道本線にも多くの支線があり、横浜から大船までの海沿いエリアを結ぶ根岸線も、東海道本線の支線(正確には独立線)にあたります。(この辺、難しいので流してください)
「じゃあ山手線は?」というと、色々な本線や独立線・支線の寄せ集めキャラ※。
「それなら常磐線は?」についても、本線級ではあるものの…、実質的に東京から東北へ向かう2番手ルートなので独立線キャラ※。
日本各地には東海道本線や中央本線のように、「ドヤ顔で本線を名乗る」線路がいる一方、独立線・支線たちは「普通に線と名乗っている」。これが実態なんです。
※本記事では一般利用者にも分かりやすく伝えるために、鉄道の正式な線籍や運行区分について、一部表現を簡略化しています。
中央本線は「線路」で中央線は「系統」



では本題に入りましょう。中央本線とは、東京〜名古屋を結ぶ「線路そのもの」を指す言葉。
じゃあ「中央線は独立線か支線ってことだね!」って…、ごめんなさい、違うんです。確かに彼らが「線と名乗っている」とは言いましたが、中央本線はドヤ顔で「本線」と名乗ってる側。
じゃあ「中央線」ってのはなんなのさ!についてですが…、これは首都圏の運行系統(路線バスの○○系統など)のこと。
中央本線という線路の上で、都内(東京〜高尾)をウロチョロしてるオレンジの系統を「中央線快速」、千葉から三鷹まで来る黄色い系統を「中央線各駅停車」と呼びます。
逆に都内を出て山梨・長野まで行く「特急あずさ」などは、新宿駅「中央本線ホーム」の発着です。つまり支線は「線」、運行系統も「線」。長距離便は「本線」。
これは「本」とに、わかりま「線」よね…。
実は東京に来てるのは「中央東線」

さて、Googleマップで都内の中央線が「中央東線」って表示されていることに気づいた人はいませんか?
実際に駅のホームに案内では「中央東線」なんて見たこともないので、あのGoogleさんも中央線にはお詳しくなかったようで…。いえ、これ事実でした。
中央本線は東京〜名古屋が一本でつながっているように見えますが、実際には「中央西線(名古屋〜塩尻)」と「中央東線(塩尻〜東京)」の二本に分離しています。
詳しい理由は分かりませんが、こちらも運行系統が影響しているような気がします。実はあの松本駅(長野県)、中央本線ではなく篠ノ井線の所属。
つまり西の列車も東の列車も、全て中央本線を飛び出して松本駅へ向かってしまう。ドヤ顔で「本線」を名乗ってるのに松本にはバキュームされ、東西で分離される。それが中央本線の実態です。
東京の電車はなぜ面倒な呼び名なの?
線路の名前と系統の名前がグチャグチャ
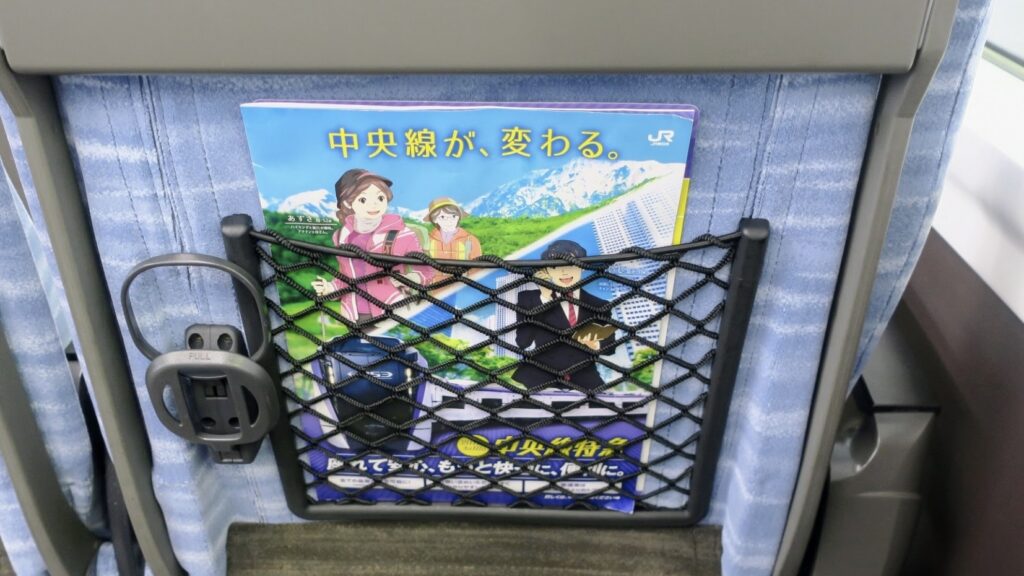
では改めて、「東京の鉄道方言がグチャグチャ問題」に取り掛かりましょう。これは、「線路名」と「系統名(運行ルート)」が一致しないせいで、利用者が混乱するという話。
たとえば宇都宮線。これは東北本線の線路を走っている運行系統の名前で、線路名ではありません。でも「宇都宮行き」ならともかく、「小金井行き」って…どこだよそれ。
京浜東北線も、実態は東北本線・東海道本線・根岸線をまたいで走る系統で、「京浜東北線」という線路は存在しません。
埼玉最強の電車、埼京線も見た目は独自路線っぽいけど、実際は山手貨物線や赤羽線などを繋いだ「寄せ集め」。
常磐線各駅停車に至っては地下鉄千代田線の中を通過して、ホームでは小田急ロマンスカーと並ぶカオスぶり。東京で電車に乗るなら、もはやスマホの乗換案内はマストなのかもしれません。
通勤と「ブランド」を優先したから

でも、なぜそんなにカオス化したのか?
もともと鉄道は、都市間を結ぶ長距離輸送を目的に整備されました。でも高度経済成長によって、首都圏内の通勤需要が激増。そのため、「通勤に特化」した運行経路が次々と作られていきました。
このとき、通勤経路の名前はシンプルな方が良いだろうと「○○線」という系統名が定着。中央線はオレンジ、山手線はグリーンといった色分けや名前が、まさに「ブランド」として機能し始めました。
その一方で「独立線・支線たちが”線”と名乗っている」という、あの件が残っています。とは言っても当時はまだ、「通勤が線」で「長距離が本線」という感覚があったかもしれません。
でも「長距離は新幹線」が当たり前になってしまった現代では、「本線」という言葉に馴染みも薄い。だから「中央線」と「中央本線」の違いを知っている人の方が、少なくなってしまいました。
「線」を「ライン」って呼び始めたJR東日本

2,000年代に入ってからも、JR東日本は新たな通勤経路を作り上げています。それは皆さんご存知の「湘南新宿ライン」や「上野東京ライン」など。
これらは元々東海道本線や東北本線、高崎線や常磐線を走っていたものを直通運転させた経路なので、「湘南新宿ライン」や「上野東京ライン」といった線路は存在しません。
まさに「運行経路」の象徴的存在です。でもこれ、もし国鉄時代だったら「湘南新宿線」や「上野東京線」などと命名されてそうじゃないですか?
そう、JR東日本は経路の「線」を英語の「ライン」にするだけで、「支線も運行経路もどっちも”線”問題」を華麗に解決しちゃったわけです。
なんなら京浜東北線は「東京横浜大宮ライン」に。中央線は「東京八王子ライン」に。埼京線は「埼玉最強ライン」とかに変えちゃえばいいのにね。







コメント